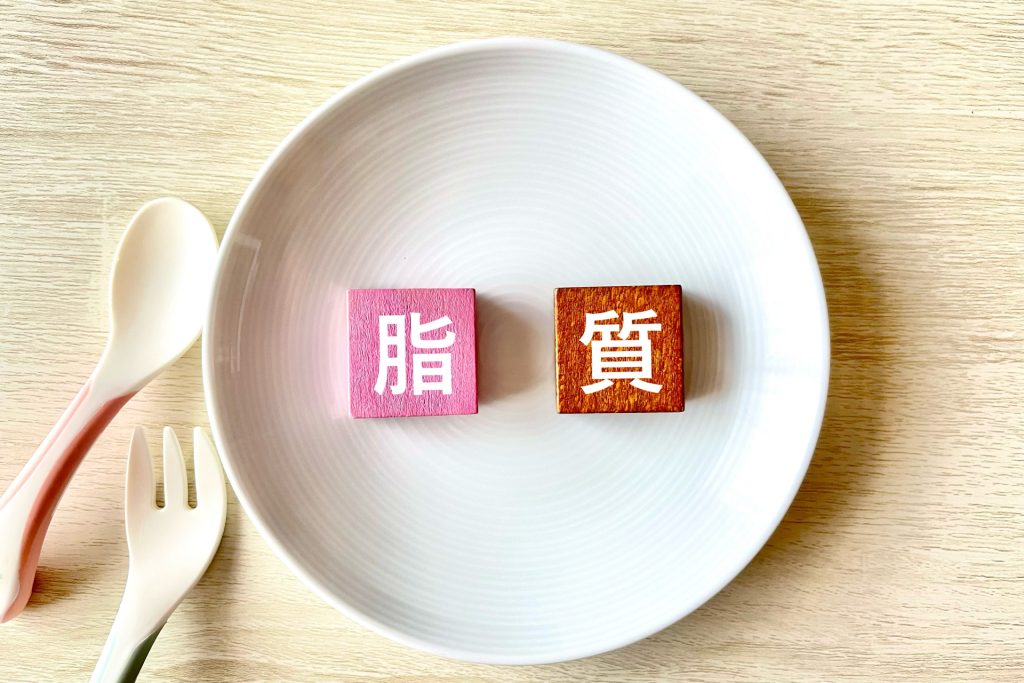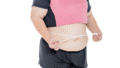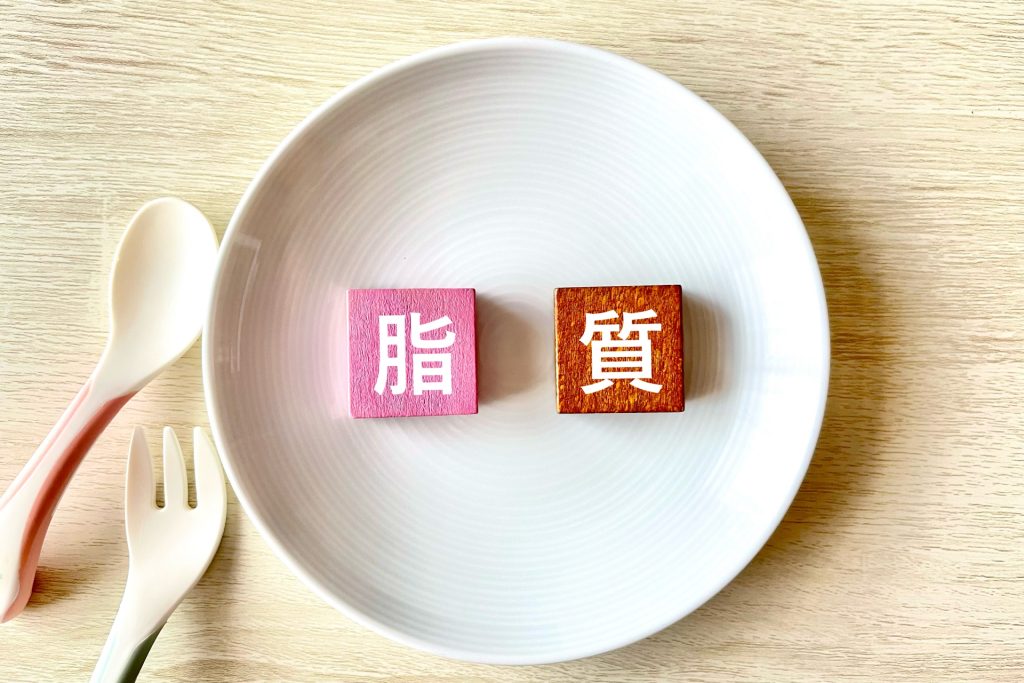
「脂質=太る」「体に悪い」と思われがちですが、脂質は私たちの健康にとって欠かせない栄養素のひとつです。重要なのは、“質”と“摂り方”です。どんな脂質が体に良くて、どんな脂質を控えるべきなのか。そして、どう摂取すれば健康的なのか。
この記事では、脂質の種類や働き、日々の食事での賢い摂り方について、わかりやすく解説します。
脂質の役割とは?体の構成とホルモンの材料になる
脂質は、たんぱく質や炭水化物と並ぶ三大栄養素のひとつで、1gあたり9kcalとエネルギー密度が高い栄養素です。
主な働きは、エネルギー源としての役割に加えて、細胞膜やホルモン、胆汁酸、ビタミンの吸収を助ける役割など、多岐にわたります。
脂質が不足すると、肌の乾燥、ホルモンバランスの乱れ、思考力の低下などの不調が現れることもあります。特に脂溶性ビタミン(A、D、E、K)は脂質がないと吸収されないため、脂質はむしろ“健康を支える存在”とも言えるのです。
まとめ
- 脂質は細胞膜やホルモンの材料になる
- 脂溶性ビタミンの吸収にも不可欠
- 不足すると肌荒れやホルモン不調を招く
「良い油」と「悪い油」その違いとは?

脂質はすべてが悪者ではありません。体に良い脂質と、控えた方がよい脂質があります。脂質の種類を理解することが、健康管理の第一歩になります。
「良い油」とされるのは、不飽和脂肪酸を多く含む油です。特にオメガ3脂肪酸(EPA・DHA)は、青魚やえごま油、亜麻仁油などに含まれ、抗炎症作用や血液をサラサラに保つ効果があるとされています。また、オリーブオイルに含まれるオレイン酸も、心臓や血管の健康に良い油のひとつです。
一方、「悪い油」とされるのがトランス脂肪酸です。マーガリン、ショートニング、揚げ物の衣に使われることが多く、過剰に摂ると悪玉コレステロールを増やし、心疾患のリスクを高めるとされています。
まとめ
- 良い油:オメガ3脂肪酸、オレイン酸など不飽和脂肪酸
- 悪い油:トランス脂肪酸は動脈硬化や心疾患リスクを高める
- 油の種類を見極めることが大切
賢く脂質を摂るための食事のコツ
脂質を健康的に摂取するためには、「揚げ物を控える」など単純な制限ではなく、“選ぶ”意識が重要です。
まず、調理にはオリーブオイルや米油などの質の良い油を選び、加熱調理では酸化しにくい油を使用することがポイントです。
また、魚料理を週2〜3回取り入れることで、自然とオメガ3系脂肪酸を摂ることができます。ナッツやアボカドなども良質な脂質源として知られています。
サラダ油や加工食品に含まれる安価な植物油、トランス脂肪酸の摂取はなるべく控えたいところ。市販品を選ぶときは、原材料表示を確認して「ショートニング」「ファットスプレッド」などの表記に注意を払いましょう。
まとめ
- 調理油はオリーブオイルや米油がおすすめ
- 魚やナッツ、アボカドで良質な脂質を
- 市販品はトランス脂肪酸表示をチェック
脂質と上手につきあうために
脂質は過剰でも不足でも不調を招く、バランスが重要な栄養素です。摂取量だけでなく、「何を食べるか」「どのタイミングで摂るか」も意識することで、脂質を“味方”にできます。
一日の食事の中で、脂質が多いメニューが続いていると感じたら、次の食事で調整することも大切です。また、空腹時に脂質を含む食材を摂ると満足感が持続し、間食の防止にもつながるというメリットもあります。
特に空腹時におすすめの脂質源は、アボカド、ゆで卵、素焼きナッツ(アーモンドやクルミなど)、サバ缶、オリーブオイルをかけたサラダなどです。これらは消化に比較的やさしく、同時にビタミンやミネラルも摂れるため、腹持ちがよく栄養価も高い選択肢です。
脂質を含むからといって敬遠するのではなく、“体に良い脂”を味方につけていくことが、健康と満足感の両立につながります。
まとめ
- 脂質は過不足ともに健康リスクになる
- 摂取のタイミングや質に注目
- 適量・良質・分散が脂質摂取の基本